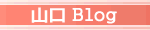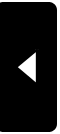最近釣り場の立ち入り禁止区域が増えています、一部のマナー違反で職業漁師の方とのトラブルも増えています。
空き缶の放置、時によっては海に流すのが心苦しいのか、ビニール袋を石で飛ばないように放置してあることもあります、仕掛けや糸はビニール袋に入れて落ち帰りましょう、海鳥の足に絡んだりして危険です、安全のためにもライフジャケットは必需品です、自分の命を守るため着用を心がけましょう。釣り場でのマナーを同釣者や子や孫に伝えていきましょう、釣りは楽しいレジャーですから。
2013年02月10日
一大ニュース!!
今朝の読売新聞を見て大変驚きました、「キジハタ捕獲制限へ 県、30センチ未満は禁止方針」なんだとか。

県は3月7日までに規制に関する県民の意見を募集するとされているが、この釣りアホの意見も聞いてもらえるんかの~。
小さいのを狙って釣るわけではないが、唇にかかったものは逃がしても良いけれど胃袋まで針を飲んでしまった個体は逃がしても生き伸びられませんで。
見島のマ○ロのように他県の網漁のように一網打尽にしないように1匹づつ趣味で釣ってどれだけ個体減少になるのだろう?(小型魚捕獲容認論ではありません)
キジハタも大型になれば沖に落ちていくので船釣りだけの狙魚になるわけで、釣りとして万人向けの魚種でなくなるわけです、高級魚が釣られるのの一部のお金持ちだけっていう風になりませんかね。
カサゴ狙いでたまたま針にかかったキジハタ、生き残れないぶんくらいは食べて往生させて貰いたいな。

県は3月7日までに規制に関する県民の意見を募集するとされているが、この釣りアホの意見も聞いてもらえるんかの~。
小さいのを狙って釣るわけではないが、唇にかかったものは逃がしても良いけれど胃袋まで針を飲んでしまった個体は逃がしても生き伸びられませんで。
見島のマ○ロのように他県の網漁のように一網打尽にしないように1匹づつ趣味で釣ってどれだけ個体減少になるのだろう?(小型魚捕獲容認論ではありません)
キジハタも大型になれば沖に落ちていくので船釣りだけの狙魚になるわけで、釣りとして万人向けの魚種でなくなるわけです、高級魚が釣られるのの一部のお金持ちだけっていう風になりませんかね。
カサゴ狙いでたまたま針にかかったキジハタ、生き残れないぶんくらいは食べて往生させて貰いたいな。
Posted by 古賀 政男 at 06:35│Comments(2)
│管理者の思い
この記事へのコメント
私が市場関係者から聞いていたのは、「職業漁師が30cm以下の個体の市場への持ち込み(捕獲・売買)を禁止する」とのことだけで、一般の趣味釣師にまで及ぶお達しではないと思っておりましたが・・・。
近年、アカミズに限らず、カサゴ、アオハタなど、栽培試験場で3~5cmまで育て放流を繰り返してきましたが、これらの魚種は長期(3年~5年以上)に渡り沿岸(放流場所近辺)に留まる為、沖に落ちて商品価値が出る大きさまで育つ前にその殆どを捕獲してしまっては意味が無いと言うことらしいです。実際、タコ漁の餌につられてタコ網に入ってしまった~10cmの個体が大量に市場に出されていました。アカミズやアオハタは元々生命力の強い魚なので、市場に並んだ時でもまだピチピチ跳ねていて、その時点でリリースしてやっても充分生きながらえます。どうせこのサイズだとせいぜい汁のだしにしかならず、当然値段もタダ同然。莫大なコストを掛けて放流するのだから「本来の商品価値になるまで捕るな」ということです。
確かに、前述の魚種は護岸からでも手軽に釣れるし、刺身サイズに至らずとも煮付けでも充分美味しいので趣味釣師には人気があるし、上手な人は数も釣りますが、所詮タカが知れています。其処まで規制する必要があるのか?それより護岸からでも気軽に高級魚が釣れる点を観光資源の1つと考えアピールするほうが経済効果が期待出来るのではないでしょうか。
昔と違って、貝類ではアワビやサザエ、ニナに至るまで、海草ではワカメやヒジキまで、一般人(漁協組合員以外)による採取が咎められる昨今(「お前らが放流したのなら名前を書いて置け」と言いたいところ)、パチンコ以外然したるレジャーのない萩に於いて、ギャンブル嫌いが静かに癒される唯一の場所を規制しないでもらいたいものです。――とは言うものの、確かに、あまりに小さい釣魚をリリースするのはお上から言われるまでも無く当然のモラルですよね。
近年の漁獲量激減の原因については単に乱獲による資源の枯渇だけでなく、気候や潮流の変化による魚群の動向の変化に対し旧態然とした漁法を続けていることにも一因があると思われ、お上も、こんな重箱の隅をつつくより、もっとやるべきことがあるのでは?と思う下層階級代表:鴨葱です。
近年、アカミズに限らず、カサゴ、アオハタなど、栽培試験場で3~5cmまで育て放流を繰り返してきましたが、これらの魚種は長期(3年~5年以上)に渡り沿岸(放流場所近辺)に留まる為、沖に落ちて商品価値が出る大きさまで育つ前にその殆どを捕獲してしまっては意味が無いと言うことらしいです。実際、タコ漁の餌につられてタコ網に入ってしまった~10cmの個体が大量に市場に出されていました。アカミズやアオハタは元々生命力の強い魚なので、市場に並んだ時でもまだピチピチ跳ねていて、その時点でリリースしてやっても充分生きながらえます。どうせこのサイズだとせいぜい汁のだしにしかならず、当然値段もタダ同然。莫大なコストを掛けて放流するのだから「本来の商品価値になるまで捕るな」ということです。
確かに、前述の魚種は護岸からでも手軽に釣れるし、刺身サイズに至らずとも煮付けでも充分美味しいので趣味釣師には人気があるし、上手な人は数も釣りますが、所詮タカが知れています。其処まで規制する必要があるのか?それより護岸からでも気軽に高級魚が釣れる点を観光資源の1つと考えアピールするほうが経済効果が期待出来るのではないでしょうか。
昔と違って、貝類ではアワビやサザエ、ニナに至るまで、海草ではワカメやヒジキまで、一般人(漁協組合員以外)による採取が咎められる昨今(「お前らが放流したのなら名前を書いて置け」と言いたいところ)、パチンコ以外然したるレジャーのない萩に於いて、ギャンブル嫌いが静かに癒される唯一の場所を規制しないでもらいたいものです。――とは言うものの、確かに、あまりに小さい釣魚をリリースするのはお上から言われるまでも無く当然のモラルですよね。
近年の漁獲量激減の原因については単に乱獲による資源の枯渇だけでなく、気候や潮流の変化による魚群の動向の変化に対し旧態然とした漁法を続けていることにも一因があると思われ、お上も、こんな重箱の隅をつつくより、もっとやるべきことがあるのでは?と思う下層階級代表:鴨葱です。
Posted by 鴨葱 at 2013年02月10日 15:10
鴨葱さん、こんばんは。
鴨葱さんのおっしゃることにも一理ありますね、市場に出さないことを当然として貰いたいものです。
魚種に詳しい釣り人は「キジハタ」だと解ってリリースするでしょうが、ファミリーフィッシングでは「珍しい魚が釣れたね、パパ食べよう」って事になりませんかね、そこで「キジハタだからリリースしなくちゃ」と子供に言ってしまっては夢を壊すような気がします。
「30センチ以下のキジハタは原則リリース」で良いのではないかと思います、規制が先走っては釣り場の雰囲気が壊れてしまいますからね。
鴨葱さんのおっしゃることにも一理ありますね、市場に出さないことを当然として貰いたいものです。
魚種に詳しい釣り人は「キジハタ」だと解ってリリースするでしょうが、ファミリーフィッシングでは「珍しい魚が釣れたね、パパ食べよう」って事になりませんかね、そこで「キジハタだからリリースしなくちゃ」と子供に言ってしまっては夢を壊すような気がします。
「30センチ以下のキジハタは原則リリース」で良いのではないかと思います、規制が先走っては釣り場の雰囲気が壊れてしまいますからね。
Posted by 釣りアホ at 2013年02月10日 20:39